吉沢亮と横浜流星の凄まじさと脇を固める役者たち
この「国宝」の面白さの要因は、何といっても歌舞伎の舞台上で魅せる吉沢亮と横浜流星の凄まじい演技だろう。
この演技をするためにどれだけの訓練をしたのかと、想像するだけで、ぞっとする。
女形として発する声だけでなく、道具の使い方や、特殊な足さばきなど、身に付けなくてはいけないことが多かったはずだ。

それに、歌舞伎役者としての演技だけではなく、舞台外での演技もすごいものだった。
吉沢亮は、好青年な見た目とは裏腹に、喜久雄に流れている極道の血の片鱗をうまく見え隠れさせている。
横浜流星は、演技に対して甘いところがあるが伝統ある血筋を受け継ぐ好青年の俊介を演じてみせる。
舞台の上と、舞台から降りた後の2人は、あまりにも雰囲気が異なる。
役者というのは、すごいなとつくづく感嘆させられた。
そして、脇を固める役者たちも豪華だった。
渡辺謙は、やはり安定感があって、存在感だけでこの映画の締まった空気を作り上げる。
寺島しのぶの演技からは、伝統を背負う女性が持たなければならない強さと、情に流れてしまう母性が綯い交ぜになったものを感じ、実は、泣きそうになった。
それ以外にも、永瀬正敏、宮澤エマや、高畑充希、森七奈、田中民など、とても豪華な面々だった。
喜久雄と俊介の子供時代を演じた黒川想矢と越山敬達も、他の名役者たちに全く引けを取っていない。

キャスティングの全てが成功して、そのキャスティングに役者の皆さんが全力で応えきったからこその大ヒットなんだろうなと感じた。
「死ぬる覚悟」がないと曽根崎心中のお初は、務まらない
それでも、吉沢亮と横浜流星の演技の凄まじさは、群を抜いていた。

それは、半二郎(渡辺謙)が病室で喜久雄に激昂して言った「お初として生き、お初として死ぬ覚悟」という言葉に現れている。
まさに2人の演技からは、死ぬ覚悟が滲み出ていた。
糖尿病の影響で意識朦朧の中、お初を演じ、袖に下がった満身創痍の俊介は、舞台を続けると周りの心配をよそに告げる。
その決意に喜久雄は、微笑む。
俊介が「死ぬる覚悟」でお初に挑んでいたからであることは、言うまでもない。
そして、お初を演じきった俊介は、命を落とす。
残酷だったのが、半二郎にしても、俊介にしても、喜久雄と同じ舞台上で2人が命を絶ってしまったことである。
まるで喜久雄が2人に引導を渡しているようであった。
私は、この半二郎と俊介の死は、対比になっているのではないかと思っている。
半次郎は、自分の口上する前に吐血し、途中で幕を引かせるということになる。
(襲名の舞台での吐血というのが、喜久雄の「血をがぶがぶ飲みたい」という言葉を連想させる。)
しかも、「お初として死ぬ覚悟」を説いた喜久雄の目前で、死を前にした自分は、舞台の上で何もできずに命を落とす・・・。
これは、今まで一線で活躍していた歌舞伎役者としては屈辱的な最後ではなかろうか。
そして、半二郎が今わの際に口にするのは、実の息子である「俊介」の名だ。
半二郎の死は、歌舞伎の業が降りかかった後味の悪いものだった。
しかし、一方で俊介の死は、確かに残酷だったが、清々しいものがあった。
俊介は、「死ぬる覚悟」でお初を演じきった。
俊介は、最後の舞台で喜久雄が求める「景色」を観ることができたのではなかろうか。
巧みな脚本と演出
役者たちの演技だけでなく、脚本と演出もすごいの一言だった。
私は、原作を読んでいないので、原作がどんなストーリーか知らないのだが、上下巻あって、分量の多い小説であることは知っている。
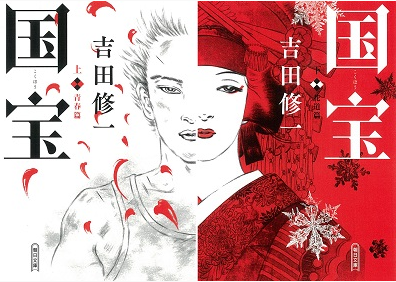
それでも、映画の約3時間に必要な部分を取捨選択し、破綻の無いストーリーに仕上げた脚本家の奥寺さんはすごいとしか言えない。
しかも、曽根崎心中を喜久雄と俊介の最後の共演作にしたのは、映画オリジナルだと言うから驚きだ。
演出の妙もその曽根崎心中で感じた。
喜久雄が半二郎の代役で出演した曽根崎心中にて、舞台上で喜久雄が才能を発揮する裏では、俊介が春江(高畑充希)と結ばれていく・・・。
春江を軸にした喜久雄と俊介の対比は、素晴らしい演出だった。
2回目の曽根崎心中での、喜久雄演じる徳兵衛が喉元にあてるお初の足と、失ってしまうであろう俊介の足を重ね合わせたシーンは、息を吞むほどだった。
歌舞伎に命を懸ける2人の覚悟が伝わってきて、圧巻だった。
同じ苦しみを共有して絆を回復するホモソーシャルな世界
喜久雄が花井家に来て間もない頃、俊介は、喜久雄に対して、なかなか心を開かない。
しかし、稽古にて半二郎(渡辺謙)からの手痛い指導を同じ場所、同じ時間に共有することで、喜久雄と俊介の距離は縮まる。
この構図は、喜久雄が彰子(森七菜)と駆け落ちのように歌舞伎の世界から飛び出した後からの展開と共通する。
喜久雄は、花井家を出ていく際、俊介に「歌舞伎の世界から逃げたお前に何が分かるのか」と投げかける。

しかし、俊介と同じように歌舞伎の世界から逃げ出した喜久雄は、その道が決して楽なものではないと知る。
歌舞伎の世界は、粋人が集まる、ドメスティックな世界だ。
一方で、歌舞伎の世界の外にあったのは、歌舞伎の魅力が通じない世界だった。
喜久雄と彰子は、出奔後、旅館などの小さな舞台に立つことで、生計を立てていた。
しかし、客のほぼ全員が、喜久雄の演技に見向きもしなけければ、一部の者は、女形という存在を「気持ち悪い」「偽物」という言葉で片付けてしまう始末だ。(嫌なシーンだった)

そんな環境に半ば精神を壊しかけ、屋上で踊り狂う喜久雄に彰子は「どこを見ているの」かと問う。
しかし、こんなつらい状況でも喜久雄の目に映るのは、支えてくれる女の存在ではなく、(おそらくだが)かつて自分がいた歌舞伎の舞台から観た景色だ。
その後、万菊に呼び戻された喜久雄は、俊介と歌舞伎の世界の外で体験した苦しみを共有する・・・。
そんなシーンは描かれないが、いつの間にか2人は絆を回復し、同じ舞台に立っている。
同じ苦しみを共有することで、2人の絆は、強固なものとなったのだろう。
このホモソーシャルな世界観は、半二郎の体罰(パワハラ)でさえ肯定してしまうものだ。
それに、こんなスポ根的な文化自体、時代とともに消えつつあるように思う。
では、なぜ、そんな時代錯誤な価値観が描かれたこの作品が多くの人に支持されているのだろうか?
時代性を反映しないからこそ100億を突破したのではないか?
ここまで時代を反映していない作品も今時、珍しいなと思った。
作中では、スマートフォンなど近年を象徴させるものが全く出てこない。
観客は、どこに共感を見出すのだろうかと不思議に思った。
それでも、ここまでのヒットを生み出したのは、先ほどの章で触れた失われつつあるホモソーシャルな世界観への羨望や懐古が要因では、決してないはずだ。
喜久雄たちが、俊介の息子への指導に半二郎(渡辺謙)の体罰を踏襲しなかったように、現代に生きる我々もそういうものから(自然に)距離をとりつつあるからである。

では、興行収入100億の要因は何か?
これまで、述べてきたように演技や脚本、演出にも、その要因があったことは間違いない。
しかし、ここまでの時代的なヒットになるには、単純な面白さだけでなく、観客がこの作品に同一の文脈を見出しているからではないか?
では、その文脈とは何か?
それは、安心ではないだろか。
それは、政治や社会から隔離されたドメスティックな歌舞伎の世界がもたらしてくれる安心である。
(人間国宝は国の制度だが、政略に使われない限り、政治色を見出し難い。)
「国宝」は、分かりやすい歌舞伎の快楽を提供してくれる。
それを味わう限り、観衆は、政治や社会、はたまた会社や家庭のことを考えることから逃れられているのではないだろうか?
少なくとも私はそうだった。
経済への憂慮や会社でのごたごたを「国宝」を観ている間は、忘れられた。
SNSに蔓延する真偽も定かでない過激な政治的投稿を忘れ、そんな投稿に踊らされる自分を忘れられた。
現実の嫌な部分を覆い隠す(もしくは、中和する)ことができる芸術の力を『歌舞伎』から借りて、うまく調理した「国宝」は、現代人の情報疲れにうまく作用し、この世紀の大ヒットをもたらしたのではないだろうか。
(そう考えるとスマートフォンが出てこないのも、偶然とは思えない・・・。)
さらに言えば、喜久雄が人間国宝となった終盤は、2014年のはずだが、震災の話も出てこないのだ。
日本人にしか分かりえない震災時の政治の文脈を描いた「シン・ゴジラ」とは、真反対の作品だった。
だからこそ、「国宝」は、「シン・ゴジラ」のようにドメスティックであるけども、海外でも通用する作品だと思っている。
果たして、邦画での興行収入歴代1位を達成できるのか。
海外での賞レースはどうなるのか。
注視していきたい。
※画像は、注釈をつけているもの以外、公式サイトより引用させていいただきました。




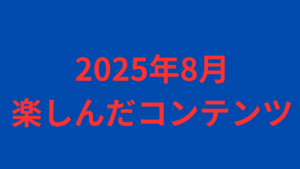




コメント