バカリズムが脚本を務める『ベートーヴェン捏造』を観てきました。
率直な感想としては、「面白いけど、物足りない」です。
記事のタイトル通り
「テレビドラマの2時間枠で放送されていたら、すごく満足できる作品だな。でも映画館で観るには・・・。」
という感じでした。
とりあえず、良かったところ、悪かったところを述べていこうと思います。
*ネタバレありです!!
良かったところ
キャスティング
キャスティングがとにかく豪華だった。
主役の山田裕貴。ベートーヴェン役の古田新太。バカリズム作品には常連の野間口徹など、脇を固める役者たちもなかなか濃いメンツだ。
市川沙耶を久しぶりに拝められて幸せだったし、染谷将太のまくしたてる喋りも良かった。
それにしても、山田裕貴は良い役者だなあと思う。
大げさに演技しているわけでもないのに、鬼気迫る感じを出せる。
あの、ねっとりした喋り方も好きだ。
テレビドラマのヒットを引きずらない潔さ
『ブラッシュアップライフ』や『ホットスポット』が評判だったので、バカリズムの強みであるギャグとしての会話劇を多く取り入れてくるのかなと思っていた。
しかし、そんな会話劇があったのは、序盤のほんの少ないシーンだけだった。
シリアスの比重が結構、重めだった。
バカリズム脚本作品では、絶対にシリアスに(傾きそうで)傾かないことがお決まりなので、驚かれた人も多いのではないだろうか。
ギャグ要素を取り入れようと思えば、もっとできたはずだ。
でも、しなかったことに私は、潔さを感じた。
バカリズムが本腰入れて脚本業をやっているのだという気概が伝わってきた。
それでも会話劇の妙は健在
それでもバカリズム特有の会話劇は健在だ。
大きな笑いが起きることは無いが、なんというか飽きさせない会話をしてくれる。
それは、豪華な役者陣があってこそだと思うし、だからこそあのキャスティングには、納得だった。
山田裕貴のナレーションもすごく良かった。
悪かったところ
中だるみする
これがウィークポイントなのだが、結構早めから中だるみする。
序盤は、物語として機能していたが、中盤からは、やや事実の羅列になる。
ノンフィクション本を物語に落とし込む難しさが露呈する。
やはり『オッペンハイマー』を時系列シャッフルして、ミステリーに仕立てたスピルバーグは、凄いなと思った。
終盤の染谷将太が登場してからは、やや物語の機能が回復するのだが、満足感が期待値に達することはなかった・・・。
中盤は、もっと工夫してほしかったと思う。
予告の期待よりスケールダウン
この映画は、純粋に歴史を描いた話ではなく、中学の音楽教師(山田裕貴)が生徒に語るシンドラーの逸話の背景として18世紀のヨーロッパが描かれる。
これは、おそらく原作からの改変だろう。
歴史は、文字や音声として伝聞される中で、矮小化されたり、捏造されたりする。
そんなメッセージを伝えるためには、良い改変だけれど、これが物語をスケールダウンさせている。
なぜなら、スクリーンの向こうにある現実は、18世紀のヨーロッパではなく、あくまで教師と生徒がいるだけの音楽室だけだからだ。
現実世界の方で何かしら動きがあれば、まだ良かったかもしれない。
例えば、空想の中の染谷将太が出てくるところで、現実世界の染谷将太を登場させるとか、そのタイミングで音楽室から3人で移動するとか。
でも、あのラストは好きなんだよな・・・。
テレビドラマの域を出ない
冒頭の話に戻るんだけど、やっぱりテレビドラマの域を出ない。
面白くて良作ではあるんだけど、映画館でお金を払ったとなると少しシコりが残る。
例えば、私は「ゴジラ-1.0」を観た時、面白くなさ過ぎて怒りすら湧いたのだけれど、劇場で観たことを後悔したわけではなかった。
それは、やっぱり映画にふさわしいスケール感があったからだと思う。
でも、それは、物語の壮大さというわけではない。
やっぱり、作品自体に映画向きか否かがあるのだろう。
もしくは、『ベートーヴェン捏造』は、映画として脚本や演出に何かが足りなかったのだろう。
そういうわけで、『ベートーヴェン捏造』はテレビドラマの域を出ていないと思った。
あとがき
どちらかというと酷評してしまったけれど、物語としては面白かったし、バカリズムへの期待も高まった。
『ホットスポット』や『殺意の過程』のような話を映画でやったら普通に面白そうだなと思っている。
これからバカリズムは、どんな映画脚本家になるのだろうか。
とても楽しみにしている。



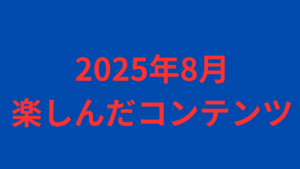





コメント