2025年上半期は個人的に色んなことがあって、まだ9月かという感じだ。
しかし、いずれ忙しかったことも忘れ、この時期に楽しんだコンテンツも忘れてしまうのだろうと思うと、なんだか時間が湯水のように流れていく気がするので、人生の一部をアーカイブしていこうと思います。
本
「庭の話」宇野常寛
上半期は宇野常寛氏の本を比較的多く読んだ。
宇野氏曰く、この本は彼の集大成になったそうで、その自評に違わずとても充実した内容だった。
読んでいて驚いたのは、宇野氏の引き出しの多さだった。
冒頭にウクライナ戦争でSNS上に生まれた架空の存在「キーウの幽霊」を引用し、中盤からはB型支援所の「ムジナの庭」、老舗の銭湯「小杉湯」、コインランドリーと喫茶店を組み合わせた「喫茶ランドリー」など『庭』の具体例を挙げて、最後には、ITプラットフォームであるGitHubが登場する。
具体例の幅が広いから、この本の内容を信頼でき、宇野氏の誠実さを感じた。
共同体に属するか否かの二元論でしか世の中を考えられなかった私にはとても良い処方箋となった。
「2020年代の想像力」 宇野常寛
「街とその不確かな壁」から「リコリス・リコイル」まで2020年代に話題になった作品の批評集である。
「この世界の片隅に」は好きな作品だったので、宇野氏の批評には、蒙を開かされた気持ちだった。
確かに「この世界の片隅に」のような作品を無条件に称賛しておけば、称賛している自分はセンス良い人間だと周りに示すことが出来る。
そんな下心をもって、私は「この世界の片隅に」を繰り返し観ていたのかもしれない。
どんな素晴らしい作品にも批評的な視点は捨ててはいけないのだと諭された本だった。
「世界一流エンジニアの思考法」 牛尾剛
プログラマの端くれなので読んだ本。
マイクロソフトで働いている牛尾さんがどうやってアメリカのつよつよエンジニアと一緒に仕事しているか、その極意を綴ってくれている。
結局は、コードへの理解が重要なのだという牛尾さんの教えには、確かにそうだよなと思わされ、いろんなプログラミング言語に手を出そうとしていた私は戒められる気持ちだった。
「フォン・ノイマンの哲学 人間のフリをした悪魔」 高橋昌一郎
映画「オッペンハイマー」を観て、ノイマンが出なかったことがずっと気になっていたので、読んでしまった。
読んでいてノイマンの壮絶な人生より、彼の超人っぷりに驚かされた。
幼少の頃から既に歴史書を暗唱できたり、何桁もの暗算ができたりと同じ人間なのにここまで違うのかと、レベルが違い過ぎて逆に生きる希望すら湧いてきた。
タイトルでは悪魔だなんだと言われているが、コンピュータだけではなく、今の豊かな生活が送れているのは彼のおかげなんだなと頭が上がらない気持ちになった。
「母性のディストピア Ⅰ接触編」 宇野常寛
この本を読むまで、日本の戦後史とアニメ史を結び付けて批評するなど思いもつかなかった。
最初は荒唐無稽と思っていた母性への依存と戦後日本人の表現の限界の関係を宇野氏の説得力のある論理で納得させられた。
この本のおかげで「攻殻機動隊」という素晴らしい作品に出会うことができた。
「母性のディストピア Ⅱ発動編」宇野常寛
「シン・ゴジラ」の批評が好きだった。
これは、宇野氏のオタク論とインターネット論に繋がるのだが、今のオタクに足りないのは、WEB1.0の時代にオタクたちが持っていた世界を情報の集積としてとらえる姿勢なのだという。
そんなWEB黎明期の頃のオタクたちは絶滅寸前だが、「シン・ゴジラ」でゴジラと戦う官僚たちは、まさに東京を滅ぼしつつあるゴジラを(災害を)情報として捉え、対抗戦略を考え、結果としてゴジラを食い止めるに至る。
庵野秀明がどんな思いでこの作品を作ったのか。
その一端が分かる名著だった。
アニメ
攻殻機動隊
宇野氏の著作「母性のディストピア」で取り上げられていて興味を持った作品。
Youtubeで配信されているStand Alone Complexを観ているのだが、主人公の草薙素子はじめとする登場人物たちが渋くてかっこいい。
大半の人が脳をクラウドで繋いでいる(電脳)時代の公安9課の活躍を描いているのだが、作中の設定は西暦2030年あたりともう現実が追いつきそうになっている。
この作品が作られたのは2000年代初めだったためか、通信機器はガラケーのままで、やはり想像力というのはその時代のテクノロジーに縛られるのだなと思った。
このあたりがどう更新されるのか。
アニメの新シリーズが楽しみである。

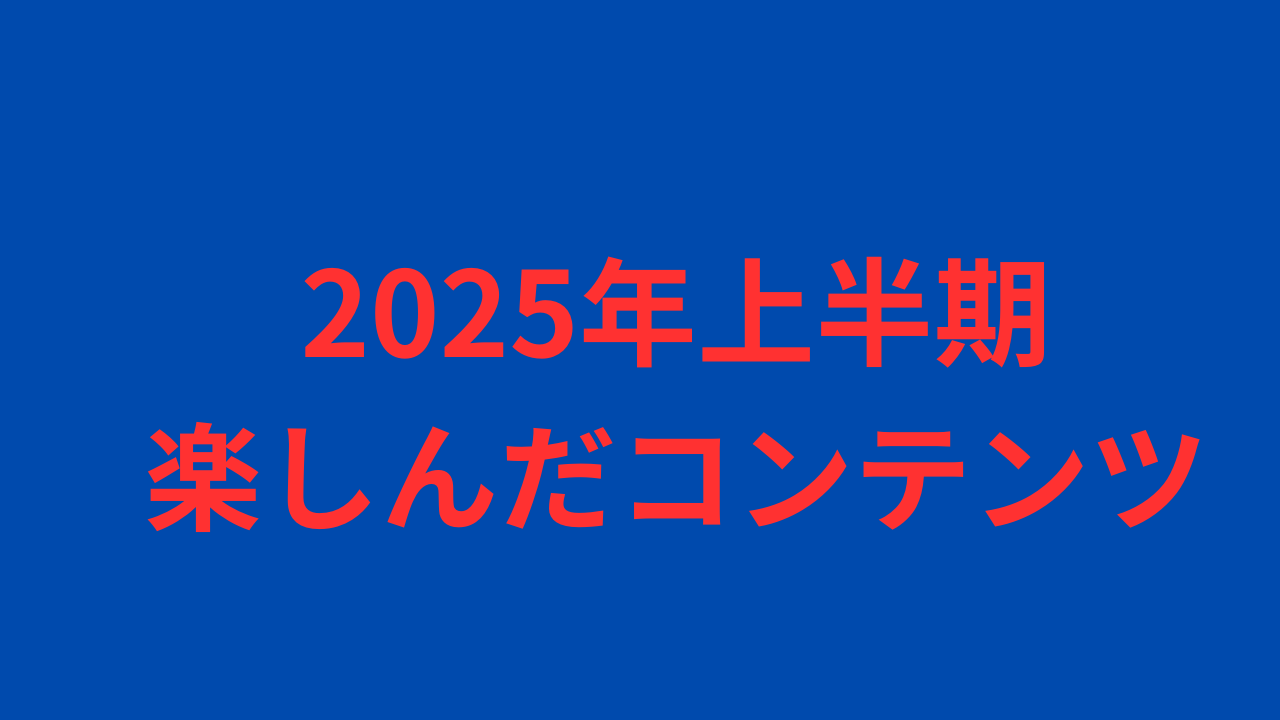


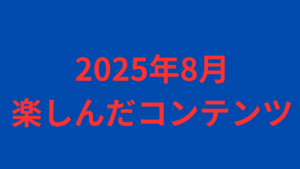



コメント