映画『8番出口』を観てきた。
とても楽しめた。
物語性の無いゲームをちゃんとエンタメ作品として仕上げつつ、社会性のあるテーマを取り込んでて凄いなと唸らされた。
“派遣社員”、”喘息”、”女子高生”などをテーマにいろいろ語っていきたい。
観る前から楽しい
まず、デザインを観ていて楽しいなあと思った。
黄色の背景に矢印と数字を並べただけのものだが、これがシンプルですごくいい。
これを基調とすることで、『8番出口』というコンテンツ全体に統一感が生まれて、スタイリッシュでかっこよくなっている。
登場人物の少なさや、場面の少なさがもたらすコンパクト感もそんな統一感と相乗効果を発揮していると思う。
公式Webサイトやパンフレットを見ているだけで、劇場で観たい欲を掻き立てられる。
監督・脚本を務めた川村元気は、公式サイトでこう述べている。
「2023年の12月に原作となるゲームを発見した時に、なんて素晴らしいデザインだろうと感銘を受けました。日本の無機質な地下通路。そこが無限にループして、次々と『異変』があらわれる。世界中の都市生活者にとっての根源的な恐怖を描けると思った。ルールはあった。デザインもあった。ただ、物語がなかった。この空間に適した物語を発明できたら、前代未聞のユニークな映画になるし、自分が撮る意味があるんじゃないかと思い、KOTAKE CREATEさんに相談しながら作っていきました。」
川村元気の慧眼恐るべしだ・・・。
そして、もちろん、作品自体も楽しんで観た。
冒頭でも述べたことだが、ちゃんとエンタメ作品として、仕上げつつ、社会性のあるテーマを取り込んでいることがすごい。
デザインや予告だけの出オチで終わらず、しっかり中身のあるものとなっている。
「おじさん」は、なぜ「歩く男」になったのか
※ここからは、ネタバレ含みます。
観終わった後、改めて「おじさん」が「歩く男」になってしまった経緯について考えてみた。
『8番出口』に出てくる分かりい異変たちは、迷った人々の無意識下のネガティブな感情を具現化したものだということは、言うまでもない。
そんな異変の一つが、「おじさん」の前に現れた女子高生(?)の存在だった。
女子高生の言葉が、「おじさん」が「歩く男」になる契機となる。
「毎日、満員電車に乗って、同じことの繰り返し。かわいそう」
そんな趣旨の言葉を、女子高生は繰り返し、「おじさん」に語り掛けるようになる。
そして、その内、女子高生の声は「おじさん」の声に変わる・・・。
女子高生のこの言葉は、「おじさん」が内心で自身に抱いている思いであることは、明白だ。
毎日のように満員電車に揺られ、会社と自宅の往復の繰り返し。
そんな自分を内心では、惨めだと思っていた。
そして、「おじさん」のそんな気持ちを代弁したのが、女子高生だったというのがミソだったと思う。
女子高生というのは、中年男性にとって、対照的な存在だ。
男はただでさえ、若い女性の目をついつい気にしてしまう。
だが、大半の男性は、女子高生に興味を持ってもらえない。
むしろ、蔑みの対象として目を向け、時には、言葉を投げかける。
おそらく、「おじさん」は、通勤や退勤途中で見かける女子高生の目を気にしていた。
「ほんとにここから出たいと思う?」
女子高生のこの言葉も当然、「おじさん」の深層心理だ。
そして、その言葉から逃げた「おじさん」は、偽物の出口を発見し、少年の制止を払いのけ、脱出を試みる。
結果として、自分の内面と向き合えなかった「おじさん」は、8番出口を彷徨う「歩く男」になってしまう。
同じところを歩いては、特定の位置で立ち止まり手慰みにスマホいじるだけの存在になってしまう。
多分、「おじさん」が現実世界で送っていた生活とほとんど変わっていないのだろう・・・。
子供の目線に立てた「迷う男」と立ってなかった「歩く男」
この映画のキーパーソンは、何といってもあの「少年」だ。
彼が大人に分からない(物理的な)視点で異変を発見することで、二宮和也演じる「迷う男」が脱出の助けとなった。
映画を観終わった後に気付いたことだが、「迷う男」と「歩く男」は、対照的な存在となっていた。
まずは、単純だが身長を含む身なりにある。
「歩く男」を演じる河内大和は、身長が178cm。
それに対し、「迷う男」の二宮和也は、身長が168cmと一般的だ。
この身長差が、あのドアノブの異変の発見に気付けた一助になったのだと思う。
加えて、河内は、髭の蓄えた大人っぽい顔つきだが、二宮は、童顔に近い。
そして、スーツとパーカーなど服装も対照的だった。
少年が、「迷う男」に心を開いたのは、「迷う男」が過去を明し、「少年」に心理的に接近しただけではないはずだ。
「歩く男」も再三、「少年」の目線に立ち、優しく語り掛けていた。
おそらく、「迷う男」の中にある幼さが「少年」と距離を縮めるカギとなったのだ。
「迷う男」はなぜ派遣社員なのか
では、なぜ「迷う男」は、幼さを保てたのに「歩く男」は、失ってしまったのか。
それは、「歩く男」が毎日、同じオフィスに通う会社員であったのに対し、「迷う男」は、定期的に仕事場が変わる派遣社員であったからだと思う。
『8番出口』では、幼さは、大人には無い視点として表現されていると感じる。
そして、この映画では、
同じことの繰り返し=大人の凝り固まった視点
という構図が成り立つのではないだろうか?
派遣社員は、確かに経済的にも社会的にも不安定な存在だ。
そして、安定のしない生活を送ることになる。
しかし、安定しない生活だからこそ失われないものもある。
職場に適応しないからこそ、失われないものもある。
「迷う男」は、スーツを着て、同じことを繰り返さない存在だからこそ、「少年」の視点に立てた。
だから、『8番出口』から脱出し、満員電車の中で赤ん坊の泣き声に苛立ち、その母親に怒鳴りつける「歩く男」的な存在と対峙することができるのだろう。
あとがき~なぜ「迷う男」は喘息なのか~
ちょっと、こじつけすぎたが、いかがだっただろうか?
あと一つ、この場を借りて、触れたいことがある。
それは、なぜ「迷う男」は喘息なのか、ということだ。
私も幼いころ喘息を患っていた過去があり、あの苦しみを痛いほど味わってきた。
だが、喘息というのは、幼少期に患いやすいが、成人に近づくにつれて治りやすい傾向がある。
私も、成人する頃には、寛解していた。
なぜ大人である「迷う男」は喘息なのか?
私は彼の中にある「幼さ」のメタファーだと考える。
(これは、「迷う男」が幼少期からの喘息を引きずったままだとした場合だけ成り立つので、説として、少し弱いかも・・・)
そうだとすると物語終盤で、喘息を克服している(ようにみえた)「迷う男」は、良い方向に成熟できたと捉えることもできるのではないだろうか。




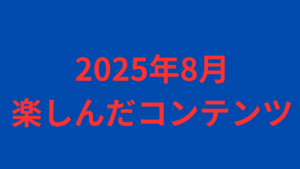




コメント