2025年もすでに9月であるが、今更ながら2024年に楽しんだコンテンツをまとめていきたい。
本
「プロジェクト・ヘイル・メアリー」
傑作だった!
この作品を魅力的にしている要素の一つに異星人ロッキーの存在があった。
人類が初めて見るなら逃げ出したしくなる見た目をしていて、最初は感情移入できんなと思ったが、読んでいくうちに彼の天真爛漫な言動の虜になってしまった。
今でも突然、「幸せ」が頭に降りてきて、思い出し笑いをしてしまう。
しかし、この作品を読んで頭が良い人への羨望を感じてしまった。
私もプログラマの端くれだが即席で異星人の言語を解析するソフトウェアを開発することなんて逆立ちしてもできない。
私が宇宙に行っても何もできないだろう。
そして、ロッキーからも逃げ出すだろう。
何はともあれ、映画が待ち遠しい。生き甲斐である。
「火星の人」
「プロジェクト・ヘイル・メアリー」が面白かったので、同著者の過去の名作を読んでみた。
結論として「プロジェクト・ヘイル・メアリー」ほどは刺さらなかった。
科学でサバイブしていくわくわく感は序盤だけで、話の重点としては、火星に置いてけぼりになった主人公の救助方法を決定するための政治的プロセスにあったように思う。
それはそれで面白かったし、アンディウィアーはこんな話も書けるのかと感嘆したが、求めているのはそこじゃないんだよなあ。
読んで勉強になったことがあった。NASA長官のメディアの使い方である。
主人公の情報は極力公表したくないのだが、あまりに渋ると世論を味方につけることができない。
世論をある程度、味方につけないと、主人公の救出に予算や時間を割くことができないのだ。(NASAは公的機関なので)
私が社会との関わりで軽視していた部分を教えてくれた。
「君が手にするはずだった黄金について」
小川哲は直木賞をとるまでは、SF作家として有名だったが、賞を取って以降は、私小説的な領域に挑戦している。
小川の引き出しの多さに驚かされた一作だった。
文章が分かりやすく、専門用語が出てこないので、彼の過去作と比べ肩ひじ張らずに読める。
なので、文章から純粋に人間の醜さを味わうことができる。
今後、彼がまたSF作品を書くときには、一味違う作品が誕生するのではないだろうか。
「ゲームの王国」
ポル・ポトの隠し子である少女と片田舎で生まれた天才少年が共産主義に支配された社会の中にゲーム性を見出していき、少女は政治の世界へ、少年は真に公平なゲームを追及していく。そんな2人は、やがて宿敵として邂逅する。
個人的には物語の筋を上記のように解釈た。
ゲームに対しての哲学的な考察が面白く、さすが東大大学院で哲学を学んだ作者だと感心した。
歴史小説は何度か司馬遼太郎を読もうとして幾度も断念したことがある私だが、歴史改変系SFである今作は楽しむことができた。
「地図と拳」
小川哲の直木賞受賞作。
あくまで史実にそった話かと思いきや突如として現れる空想的な挿話がこの物語に不思議な魔力を与えているような印象だった。
マジックリアリズムと呼ばれる手法で昨年、文庫化で話題を集めた「百年の孤独」にはこの手法が用いられているらしい。
孫悟空も好きだったのだが、やはりキーパーソンは細川で、細川に始まり、細川に終わる物語であった。
「君のクイズ」
小川哲が直木賞後に発表したミステリー作品。
クイズ番組で対戦相手がなぜ0秒回答をすることができたのかを主人公が解き明かしていく。
この本を読んでクイズ番組への印象が180度変わった。
クイズ番組に関わる全てにクイズに関するヒントが隠されていると知れた。
話の着地点としては、驚愕の真実!という感じではないのだけれど、とても納得のある終わり方だった。
「テスカトリポカ」
神奈川県川崎を舞台に裏社会のやべー奴らが心臓密売ビジネスに手を出すというクライムノベル。
「地図と拳」と一緒に直木賞を受賞した作品である。
映像化を意識したという今作は、確かに描写が立体的で映像映えしそうな箇所がいくつかある。
読んでいるだけで映像が浮かんでくるので、とても状況をイメージしやすく読みやすい。
アステカ神話の血なまぐさい感じが作品の基調となっていて、宮部みゆきが本作を「燦然と輝く黒い太陽」と評したのも納得だった。
映画
「哀れなるものたち」
上映館が意外に少なくて、メジャーな映画館ではやっていなかったので、柏駅近くにあるキネマ旬報シアターというところで観覧した。
なかなか雰囲気のいいところだったけど、前の座席との段差が少なくて、少しスクリーンが見づらかったのが、悔やまれるところだった。
それはさておきとして、映画は面白かった。
世界観がサイケデリックで最高で、モノクロ描写の工夫など、演出にもどこまでも抜かりはない。
「哀れなるもの」というのは、母性的なものに依存してしまい、社会的なことを考えられなくなる男性性のことなのだろうか?
※家族で観るな!!
「オッペンハイマー」
思っていたより盛況で、おかげで映画館の一番前の席で観ることとなった。
とても観にくかった。
事前に席を予約していなかった私が悪いが、公開から1か月以上たっていたからさすがに予想していなかった。
しかも、カップルも多かったので驚いた。
内容は、予想以上に面白く、事前に聞いていたような説教臭さや原爆投下へのアメリカの自己弁護などは個人的には、あまり感じられず、エンタメ作品として楽しめた。
話の軸に「マンハッタン計画の安全保障委員会聴聞会」据えたのは意外だったけど、その意匠は見事に成功していている。
あの緊張感のある雰囲気を作り出す役者の演技や演出はすごいとしか言いようがない。おかげで一番前の席で観ていたことを忘れていた。
批判的な意見が思いつかなかった私には、PLANETSの批評座談会での宇野氏の批評には膝を打つ思いだった。
「メッセージ」
原作「あなたの人生の物語」を読んだので、こちらもprime videoで視聴。
原作とは、設定が異なり、壮大な話になっていた。
しかし、軸となる部分は変わらず、映画の方がSF的な興奮を味わえた。
宇宙人の造形や言語要素など、もしかしたらアンディウィアーの「プロジェクトヘイルメアリー」はこの作品を少し意識しているのかもしれない。
ただ高い重力下では、蜘蛛型が生物の形として効率らしいから、偶然という名の必然かもしれない。
「未来を知るから、未来を変えようとするのではなく、予知した未来に惹かれるようにして、その筋道を辿ってしまう」という解釈に目から鱗だった。
「TAR」
話が2重構造になっていて、騙された。
観れば、気に入らない人を蹴落とす快楽を自分が持っていると知れる。
ただその人を気に入らないという理由だけで事実など関係なく、だ。
あまり語るとネタバレになるので、とにかく観てほしい。
漫画
「売国機関」
この漫画を読んで初めて推しという存在が理解できた。
誰を推しているのかというと、それは、もちろん主人公のモニカ・シルサルスキである。

番外編より
架空の国の戦後を描くフィクションだが、主人公モニカの住むチュファルテク合同共和国はポーランドをモデルとしているらしい。
クライス連邦、ガルダリケ王国という強国に挟まれているチュファルテク合同共和国は、戦後の今、両国からの干渉と戦っている。
それに立ち向かうのが、モニカの属する「オペラ座」という部隊だ。
「売国機関」は、癖の強い人物たちの集うオペラ座とそこに新しく赴任したモニカを中心に描かれる。
軍事学校を首席で卒業する秀才であるモニカが、オペラ座の荒波に揉まれ成長する姿に私は「推す」という概念を見出した。
また、モニカは大食漢である。それも彼女の魅力である。
(カルロ・ゼンは天才)
「ありす、宇宙までも」
読んでいて純粋に主人公の二人を応援したくなる。
知識の大切さではなく、知ることの面白さを描いてくれてるのが、とても良い。
ただ、私は「宇宙兄弟」のように世間に自己啓発的な受容をされてほしくないなと思う。(宇宙兄弟は好きな作品なのだが・・・)
作品に変な先入観を与えてしまうし、あくまでフィクションの世界の主人公の振舞いをリーダーの理想として捉え称賛するのは、果たしてどうなのだろうか。
この漫画から自己啓発の要素を見出す必要はないし、意識高い系界隈の人たちからおもちゃにされてほしくない。





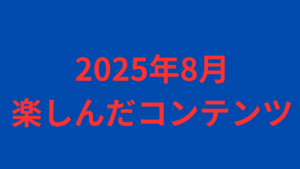
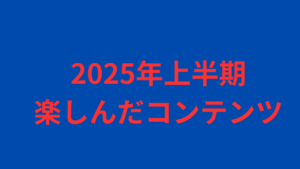



コメント